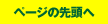エキゾチックなSEにのって登場したのは、全員90年代生まれの4人組、The SALOVERS。「こんにちは、サラバーズです、よろしく」という、フロントマン・古舘佑太郎(Vo・G)のあいさつとともに、1曲目の“サリンジャー”がスタートする。火を噴くように爆裂な疾走感溢れるサウンドを、古舘のちょっとしゃがれたパワフルなボーカルがさらに後押しする。フェスらしい、ゆるりと開放的なムードでいっぱいだったSEASIDE STAGEの空気を一気にぶち破って、キリキリとした緊張感漂う、己の世界を炸裂させた。若きニューカマーだが、そのアンサンブルは豪快にして独特の迫力を持っている。続く“狭斜の街”でも、すさまじくガッツのある藤川雄太のドラムを筆頭に、藤井清也のアグレッシヴなギターと小林亮平のぶっといベースで、あらゆるものをなぎ倒すかの勢いで突き進んでいく。“フランシスコサンセット”はチューニングがズレて気持ちよく演奏できないから、と仕切り直した。フェスの大舞台ながら1ミリも動じず、とにかく全身全霊で立ち向かっている。彼らの歌の世界、音楽の根っこそのものといったふうだ。
「出番前はお客さんがいなくてパニックで、1曲目はぬるっとやっちゃったんだけど」「最初のほうはイマイチだったけど、最後の曲に懸けたいと思う」と、なにげに弱気な(?)、いまいち納得のいってないような発言をした古舘だったが、いやいや、これがぬるっとした演奏だとしたら、君らの本気はステージがぶっ壊れると思うよ、というくらい4人のアンサンブルは、いい。フェスだから楽しく、いや、手放しで楽しんでしまえ!という思考回路はどうやら存在していないようで、つねにストイックで、真っ向勝負。まあ、だからこそこの怒涛のアンサンブルが構築されるんだろう。がっちりと肩に力が入っているが、それが暑苦しいものじゃなくて、非常に好感が持てるし、信頼できる。この先、さらに面白いバンドになっていくだろう。ふつふつと怒りや退屈に沸き、煙の出そうな4人のロックンロールを聴きながら、そう思った。(吉羽さおり)


The SALOVERS のROCK IN JAPAN FES.クイックレポートアーカイブ