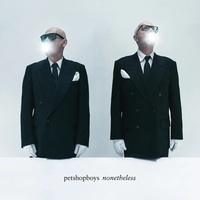photo by 笠井爾示(KATT)
photo by 笠井爾示(KATT)圧倒的なサウンドに打ちのめされながら、このアルバムについていろんな人と話して、SNSにポストされる評を見て、みんなが言っていることはその通りだなと思った。けれども、あともうひとつ言い当てている感じがしない。自分は、何にこれほどまで揺さぶられているのだろう? 『Gen』を聴いていると、「参った」という降伏する気持ちと、心の奥底で共鳴するような気持ちがないまぜになって、自分の心の輪郭が膨らんだり縮んだりするような不思議な心境になる。落ち着かない。これは一体……と途方にくれていた時、本誌(『ROCKIN'ON JAPAN』2025年7月号)インタビューを読んで、突然視界が開けたような気になった。星野源が「伝えたいこととかメッセージがないんですよ」と言い放っているフレーズに出くわし、得体の知れない感情がぶわーっと、身体中を駆け巡ったのだ。
本作は結局のところ、何を成し遂げているのか。この際はっきり言いきってしまうなら──つまり、意味過剰な今の世の中における「無意味の自由」を、表現の最後のフロンティアとして掲げているのだ。これがどれだけ画期的なことなのか、説明していこう。
まず、今作『Gen』の制作はシングル“創造”に端を発しており、つまり2020年くらいから開始されている。2019年、彼はコラボレーションを通して試行錯誤した実験作『Same Thing』をリリース、ワールドツアーも行った。『Gen』の時代はそのあと、コロナ禍から始まっているのだ。2020年から、2025年。狂った6年間だ。何が狂っているかって、政治も経済も何もかもなのだが、ひとえにSNSを中心とする言語空間が異常をきたしたというのが大きいだろう。端的に言うと「意味過剰社会」になったわけで、どこもかしこも意味と記号に埋め尽くされてしまったのである。誰かの言動に倫理的正しさや間違いを貼りつけるような意味づけが常態化し、批判と炎上の道徳ゲームが始まった。出来事や作品をめぐって即座に「これは何を意味するのか?」という分析が繰り出される解釈・考察文化も加速した。さらには、人々が自分を「〜系」「〜推し」「〜クラスタ」のように「意味ある何か」として定義し合う記号とラベルの競争も定着した。これらはすべて、意味のあるものが世界を作っているという前提が無意識に共有されており、結果、あらゆる表現が意図や訴えや立場表明を求められるようになった。ただ、日常のすべてがエンタメ化していく面白さがある一方で、それは、なかなかしんどい状況だ。なぜなら日々の一挙手一投足に意味づけされるなんてたまったものじゃないし、特に、本来はもっと自由であるべき創作においては、意味を拒否したり意味を担保したりしないことにリスクが生まれるようになってしまったから。すぐさま「何が言いたいの?」と詰められ、意味がわからないものは価値がないと切り捨てられ、メッセージがないものは社会性がないと批判される。あるいは、思いもよらなかった意味づけをされて悪者にもなる。その結果、2025年現在、世の中はこのありさまだ。私たちは意味に疲弊し、先のインタビューで星野源は「どうでもいい」とまで言っている。
そのような状況下で、『Gen』の制作がドライブし始めたのは、まずコロナ禍でのDAWを使ったクリエイティブだった。「創作の楽しさは唯一残っている」と言う彼は、まさしく子どもが遊びに没頭するかのごとく、ピュアな心で音楽制作に突き進んでいった。本作ではその楽しさが堂々と宣言されており、1曲目の“創造”が発する躍動感には思わず笑みがこぼれてしまう。《何か創り出そうぜ 非常識の提案》という歌詞とともに弾ける電子音、四方八方で鳴る音の祭り。楽しい。なんて楽しいんだろう。星野源自身がDAWで音を出すことを楽しんでいて、そのバイブスがこちらにまで伝播してくるという幸せな音空間だ。
そしてもうひとつ、『Gen』を捉えるうえで重要なのは、海外アーティストとの交流だろう。本作ではルイス・コール、サム・ゲンデル、サム・ウィルクスというLAジャズ〜エクスペリメンタルの気鋭ミュージシャンをはじめ、多くの海外勢とのコラボレーションが実現しているが、そこで聞こえるセッションは実にオーガニックだ。特にイ・ヨンジとの“2”、UMI、カミーロとの“Memories”といった曲に漂うナチュラルな柔らかさは、リラックスした空気に満ちている。その結果、本作には、虚無を前提としつつも「訴え」や「自己表現」から解放された星野源がいる。DAWを使った純粋な創作の楽しさに没頭し、気を許した海外アーティストとの関係の中で得た安心感と自信を土台に、世界をただ「あるがまま」に記述する地点に立った姿! “Mad Hope”を聴いてみてほしい。この歌詞、この歌、この演奏。意味なき音楽の極致のようだ。
誤解しないでほしいのは、本作での星野源の姿は単なる諦念ではないということ。このアルバムから伝わってくるのは、「世界に意味はない」ことを受け入れた地点から、なお生を選び創造する自由さである。星野源の語る「言いたいことがない」という虚無性は、不条理を直視しきった人間の言葉だ。その証拠に、彼は「意味」を手放した一方で、「関係性」については大切に扱っている。DAWはまさに音の断片を結び、解き、重ねていくネットワーク的創造であり、海外アーティストとのコラボレーションも、「自己表現のため」というよりは他者との接続そのものが創造の源泉になっているではないか。
だからこそ、伝えたいことも訴えたいこともなく、信じる関係性をもとにただ状態を書いているだけの意味なき創作が「楽しい」という姿勢は、現代の意味至上主義へのラディカルな応答となっている。これは、単に意味を拒否する態度ではなく、意味で埋め尽くされた世界において意味から解放されるための倫理であり、表現過多の時代における表現なき創造の可能性でもあろう。それに、「意味を込めない」という行為はある種の勇気であって、誰かに「こうあるべき」と指図しないという点できわめて優しい態度でもあると思うのだ。“Sayonara”を聴くと、冒頭のピアノから優しさが滲み出て安心すると同時に、そこまでたどり着いた星野源の覚悟に恐ろしくもなる。彼が今立っている地点は、私たちを覆い尽くす意味の洪水の中で、意味を解体し尽くしたあとでなお、軽やかに創造するのだという姿勢そのもの。これは、ノイズまみれのSNS時代において、「伝えなくてもいい」「意味なんてなくていい」「ただ音がある」「ただ遊ぶ」という静かなレジスタンスであり、あるいは、21世紀の新しい「精神の気品」と言ってもよい。そう、『Gen』には気品がある。意味と戯れることを捨てた境地へとたどり着いた者しか成し得ない、気高さがある。
この境地は、誰もがたどり着けるものでは到底ない。なぜなら、『Gen』の放つ気品は、意味なき「無」の音楽でありながら、サウンドそれ自体は豊潤なハリに満ちているから。この点が、本当に素晴らしい。たとえるなら、無地の布が風を受けてふわっとふくらんでいるかのような状態、と言えるだろうか。何も語っていないのに音が空間を満たし、感情の輪郭を浮かび上がらせるさまに近いのだ。どうして、そんなことが可能なのか?
繰り返しになるが分解していくと、この豊潤なハリは、彼の中でDAWによる鍵盤作曲が定着したのが大きいだろう。これまでギターで曲を作っていたところを、DAWを使うようになりキーボードでアプローチし始めたことで、ギターで出せなかったニュアンスを生み出せるようになった。つまり、鍵盤とコンピューターは、星野源の身体とほぼ一体化したのである。ギターという「楽器」を駆使していた時代から、DTMによる「音のイメージと身体とが同期する」時代へ。これが、大きなパラダイムシフトを生んだのだ。
結果的に、『Gen』は、過去作と比較していささか歪だ。『YELLOW DANCER』(2015年)や『POP VIRUS』(2018年)のサウンドのほうがアルバム全体としてトータルプロデュースされている感があり、サウンドのトーンも揃っている。『Gen』は、もっとバラバラで、起伏に富んでいて、躍動している。トゲトゲしたビート感が粒立っている“Glitch”のような曲がある一方で、“暗闇”のような弾き語りの曲すらある。その“暗闇”では《あなたの涙から/流れるきたない心》という歌詞が飛び出してぎょっとするのだが、考えてみれば、これはきれいな音も汚い音もどちらも共存するアルバムである、とも言えるだろう。そして、そういった点こそが、本作に漂う気品であると思うのだ。
現代社会が目指すクリーンさや正しさは、しばしば美しさの片面=表層の整合性や衛生感だけを追い求め、矛盾・汚れ・歪み・感情の濁りといった「人間的な陰影」を排除しがちである。しかし、本来的な気品であり気高さとは、そうした「汚れの排除」の先にあるのではなく、むしろ「きれい」と「汚い」、「静けさ」と「狂気」、「秩序」と「ゆらぎ」といったその両方を引き受け、共存させているものにこそ立ち上がるのではないだろうか。つまるところ、表面だけきれいにして「意味」を整えたものなんて、本当の意味で気品ではないと思う。『Gen』には、そういった気高さなるものの正体が宿っている。虚無の心象風景をそのまま受け止めたうえで、音楽としての楽しさや軽やかさ、遊びを重ねていくこと。これは、混沌の中の秩序であり、あるいは不完全さの中の統一でもあり、単なる「きれい」では説明のつかないものだ。
思えば、近年のポップミュージック自体も、「きれい=クリーン」と「汚い=ノイジー」の二極化・分別化が進んでいたと思う。DAWやプラグインの進化による完璧なピッチ/タイミング補正。高域から低域まで滑らかに整ったエアリーでリッチなミックス。ストリーミング対応に圧縮された聴きやすい音像。それらは「清潔感」や「正しさ」への志向ともどこか近いものを感じさせる。対して、ボカロミュージックやハイパーポップ、ヒップホップ的な音楽に代表される通り、音割れやスピード感、さらにはブーストされたハイとロー、オートチューンの過剰使用、「病み」「闇」「アウトロー」「陰キャ」「中毒」といった界隈の個性は、ネット感覚と結びついた反・健全/反・正常の美学として加速してきた。こちらは「汚れ」や「歪み」を逆にスタイル化したものであり、クリーンさに対するカウンターとしての戦略的「汚れ」である。
そういった二極化が進む構図において、両極だけが可視化され、「きれいでも汚くもある音」「崩れているが、優しい」「虚無だけど、しっとりしている」といった、微細で濃密な中間領域が見えにくくなっているのは確かだ。故に、『Gen』にあるような濁った清さ——音像はむしろ滑らかで整っていてミックスも丁寧だが、その中に精神的な「濁り」「狂い」「虚無」が潜んでいて、遊びや軽みも同時にあるという作品は、ポップの新しい形として機能するだろう。クリーンかノイジーかではなく、「濁りを包む透明さ」という可能性。整っているようで濁っている、軽やかなようで深く疲れている、その気高さこそが、これからのポップが進むべき領域になると思うのだ。
繰り返そう。これは本当に偉業だと思うから、何度でも反復したい。『Gen』は、音が意味を離れ、ただ遊び、ただ響いていて、その自由の中に現実の楽しさが立ち上がる作品だ。私は、そこに降伏し、共鳴した。これからのポップミュージックは、本作のような気高さを必要としていくに違いない。その新しい時代の先で、『Gen』は諸行無常のごとく存在している。ポップがまだ生きているということの、ひとつの証。破れても、揺れても、微かに美しいという、存在の証明。これは、祈りにも似たレジスタンス。(つやちゃん)
(『ROCKIN'ON JAPAN』2025年7月号より抜粋)
▼『ROCKIN'ON JAPAN』2025年7月号の表紙巻頭に星野源が登場!
ご購入はこちら
*書店にてお取り寄せいただくことも可能です。
ネット書店に在庫がない場合は、お近くの書店までお問い合わせください。