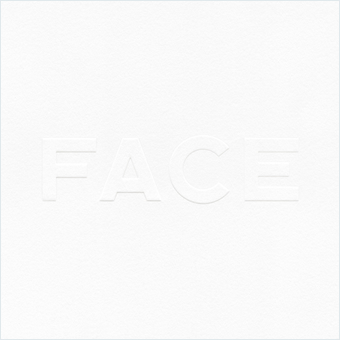- 1
- 2
ダフト・パンクのアルバムと、結局やってることは近いっちゃ近いのかもしれない……って言ったら失礼なのかな
──今回のアルバム、歌ものがすごい多いですよね。これは作っていくうちにそうなったっていう感じなんですか?


Ali& スタートするってなって、まずデモを集めるんですけど、何人かフィーチャリングヴォーカルの候補をリンクでいただいて、それぞれのアーティスト聴いてって、みたいな感じですよね。それが最終的に6人いたっていう感じですね。もしかしたら12人いたかもしんないし。
JUN 最初にデモを持ち寄った時点で、なんとなくこの曲は歌があったほうがいいなとかってやってったら、自然と6人ぐらいフィーチャリングすることになったっていうぐらいの(笑)。あえて何曲歌ものを入れようとか、意識的にそういうのを考えたわけじゃなくて、自然とって感じですね。
──歌ものが好きっていうのはあるんですか?
JUN セカンドとかだったらインストにこだわりたいとかいろいろあったけど、そんなに考えないというか、無意識に(笑)。
Ali& あと最近の自分たちがやりたいことが、やっぱり90'sの要素ももちろんあるし、R&Bの要素もあるし、今っぽい感じのものが、自然と歌が好きなものが多かったような気もするし。クラブミュージック作るより若干歌もののほうがハードルは上がるので、そのトライしてるところが楽しいっていうのもあるんじゃないですかね。
──(笑)"I Got a Feeling"はベンジャミン・ダイアモンドが歌っていて、曲の雰囲気から何からもう、思いっきりフレンチ・ハウスで。
Ali& はい(笑)。
──あれはベンジャミンへのオファーありきでああいう音にしていったんですか?
JUN もともとはオファーは考えてなくて、インストのピアノハウスじゃないけど、ピアノのテックハウスみたいなイメージで作ってたんです。でも歌があったら面白いんじゃない?っていう。いっそベンジャミン使ったら──。
Ali& やったらやったでベンジャミンからいろいろ言われましたけどね(笑)。「もうちょっとこうがいいんじゃない?」みたいな。
JUN 要求、多かったですね(笑)。
──ははははは! 贅沢な遊びっていう感じですよね。
JUN そうですね。だからそういうのもアルバムっていう大きいプロジェクトの中でしかやっぱやりづらいというか。
Ali& 向こうもたぶん、アルバムだからっていう部分で協力してくれた部分もあると思うし。
JUN だから歌ものをフィーチャリングできるっていうのはやっぱアルバムの醍醐味じゃないけど、そういう部分もあったのかなっていう。
──シンガーも結構個性豊かな人が集まっていますしね。
JUN 新人からちょっと古い人まで。
Ali& でも自然とそうなりましたね。何がなんで、みたいな感じはなかったっすよね。
JUN ベンジャミンに関しては前リミックスしたことがあって、インスタとかでちょっとつながりがあって。最初はDMというかコンタクト取って、「歌ってもらえませんか?」みたいなオファーをしたんです。
──そういえば、ダフト・パンクのこないだのアルバム(『ランダム・アクセス・メモリーズ』)は、おふたりにとってはどうだったんですか?
Ali& 僕、普通に好きでしたけどね。ダフトのアルバムっていうよりも、なんかね、ジョルジオ・モロダーとかナイル・ロジャースとかのアルバムっていう印象ですね、僕は。
JUN 人間をサンプリングしちゃったみたいな感じの。
Ali& そうそう。でも、あのアルバムがグラミー獲ったっていうことで、やっぱりEDMじゃないじゃないですか。どう考えても。すごいルーツな音楽だし、すごく音楽史においてちゃんとやってる音楽なので、それがリスペクトされてる音楽なので、僕はすーごい好きですけどね。一過性のものではないんで、たぶんあれは。そういうのをエレクトロ上がりの人たちがやってくれたって思ってるんで、素晴らしいと思います。
──自分たちがやりたいこととどこかしらリンクする部分ってあります? そういうルーツ感というか。
Ali& あるかもしれないですね。でもなんかちょっと違うよな。あれはもうちょっと歳取ってからかな(笑)。
JUN 比べものにならないんじゃないですか(笑)。比べたらいけないっていうか。でも結局やってることは、今考えたら近いっちゃ近いのかもしれない……って言ったらどうなんでしょうね。失礼なのかな。
──いや、そんな感じがしますよね。
JUN 全然考えてなかったですけど(笑)。恐れ多いな、みたいな。そう言われて。
音のスタイルはちょっと変わってきてるけど、スタンスはぶれてない。そこが重要っていうか
──"Don't Wait Up"とか"Can't Sleep"とか、すごいいい曲だと思うんですけど、このちょっとロマンティックな雰囲気というか、こういうのってもともと80KIDZの中にあったものなんですか?
JUN 前のアルバムにもちょいちょいそういう、ちょっとゆるめの曲ってあったと思うんですよ。"Lightwaves"とか。だから別になかったことはないというか。
Ali& 今回その2曲に関してロマンティックな感じがすごく出たっていうのは、結構音を少なくしてるんですよ。足したりしてないんで、なるべくアカペラが聞こえるように、無駄をすごい剥いだんで。それで結構ロマンティックな雰囲気が出たように聞こえたのかなと思いますけど。
──なるほどね。『TURBO TOWN』とは全然違う生音感っていうか、空間の感じだとかっていうのがすごくあって。"I Got a Feeling"とか"Face"とかのピアノのニュアンスみたいなのも含めて、ちょっと繊細さというかメランコリックなニュアンスがあるんだなあ、みたいな(笑)。
Ali& ありました(笑)。
──ガンガン攻める感じなのかなと思ってたから。
JUN 歳も歳だし、みたいな(笑)。
──ははははは!
JUN なんだろうね。自然となっちゃったんですよね。
──それも前作でギターがガンガン鳴ってたのとの対比がすごい面白いなと思って。それが同じ人間の引き出しから出てくるっていうのが、80KIDZの面白さだろうなと思うんですよね。さっきも言いましたけど、ほんとその時々にしっかり時代に寄り添いながら、かつ自分たちのルーツもちゃんと表現するっていうのが80KIDZなんだろうなっていうふうに思うんですけど、ご自身たちで振り返って、自分たちのスタイルは変わってきたなと思うのか、それとも一貫してるなって思うのか、どっちのほうが強いですか?
Ali& 一貫してるなあって思いますけどね。
JUN 一貫してるのかな(笑)。ぶれてはいない。
Ali& 今聴くと、あの時こうしとけば良かったなって思うのはありますけど。でも、その当時にやったスタンスと、歳を取っても常に同じスタンスでやってるなって思うので。結局、迷って「これをやったほうが評判良くなるのかな」って思いながらも、そうじゃないことをやったりしてるんで、ずっと。全部、自分たちを全肯定してもらいたいっていう感じでやってるのかな。「僕たちを肯定して」じゃなくて、「おまえら肯定しろよ」ぐらいな勢いで、「わかれ、わかれ」ってずっと作ってきたような気もしますけどね(笑)。
──それは自信なんですか? かっこいいに決まってんだろう、みたいな。
Ali& わかんない、どうなんすかね(笑)。
JUN でも音はちょっと変わってると思うんですけど、スタイルが。だけどスタンス的にはぶれてないんだと思うんですよね。そこが重要というか。
──まさにそうですよね。スタイルは変わってるけど、スタンスは変わってない。
JUN ちょっと伝わりづらいかもしれないけどね。
もともと普通に音楽めちゃめちゃ買って、ライヴ行って遊んで、みたいな感じだったんで。たぶんそこの延長線上で80KIDZが始まったし、だから何をやればいいかもわかってた
──そのスタンスっていうのは、言語化するとしたらどういうものですか?
JUN なんだろうね。シーンの中での立ち位置だったりとか、取り得るジャンルの幅とか、やっぱ僕たちが思う「好き」っていうのがぶれないっていうか、行っちゃいけないとこをやったりしないっていう(笑)。これはかっこ悪いだろうっていう線引きがやっぱ見えると思うんですよね、アルバムの中で。それが僕たちのスタンスというか、スタイルにつながるんじゃないかなっていう。
──だから時代のトレンドとの距離感も常に一定だと思うし、今おっしゃいましたけど、それこそいわゆるシーンみたいなものに対する距離感というか、批評性みたいなものも常にあると思うし。
Ali& ありますね。
──常にシーンの動きを客観的に見てるような感じが80KIDZにはあるんですよ。どっぷり浸かってないっていうか、常にちょっと引いて見てる視線が。
JUN ずるいよね(笑)。
Ali& ずるいずるい。
──まぎれもなくダンスミュージックのクリエイターなのに、そのダンスミュージックそのものをわりと冷静に見てる。それがすごい面白いんですよね。なんでそうなったんですかね。
Ali& もともと普通に音楽めちゃめちゃ買って、ライヴ行って遊んで、みたいな感じだったんで。たぶんそこの延長線上で80KIDZが始まったし、だから何をやればいいかもわかってたし、それをずーっと続けてるから、なんですかね。別にこれを作りたいっていうエゴもそこまでないんで、僕たち。こういうスタンスでこういう音楽をやるんだ!っていうわけでもないし、こういうジャンルをやるんだ!っていうわけでもないんで。その時のシーンに対してある程度の距離感だったり、ある程度のポジションだったりを踏まえた上で、やるべきこととかやんなきゃいけないことっていうのとか、変えてかなきゃいけない部分をたぶん音楽でやってるだけって感じかもしれない。
──だからすごいリスナー視点というか。
JUN まあそうですね。
──生まれ持ってのアーティストとはちょっと違うなって思いますよね。
Ali& 違いますね。
JUN 作家としてのスタートが結構遅かったんで。それまでに培ったリスナーとしてのスタンスが結構強いというか。20代中盤ぐらいまで普通にフェス行って、ライヴ観てかっこいいなと思ってたような、お客さんの立場だったわけで。そこがやっぱ強いから、そこからスタートして今に至ってるんで、そこは出ちゃうよね、やっぱりね。
Ali& DJもそういうようなもんだからね。
──なるほどね。僕正直に言いますけど、80KIDZ出てきた時に、このユニットはニューレイヴと一緒に心中していくんだろうなって思っていたところがあったんですね(笑)。
Ali& ははははは。
JUN ギリギリ生き残った(笑)。
──ギリギリどころか、すごく生き残ってるんで(笑)。今となっては大変失礼な話なんですけれども。
JUN だから頑張ってほしいね(笑)。
Ali& ははははは!
JUN せっかくだからね、どこまで行くか見たいよね(笑)。自分たちも結構客観視してるんで、自分たちの活動に対してね。
Ali& そうだね。だから何をやりたいかっていう部分での活動でもないんですよ。個人としても。自分は80KIDZがあって、自分自身があって、そういう世の中があって、何をしたらどうやってこうなってこうなるんだ、みたいなのはよく考えるんで。ま、結論ないですけど。でもそこのライン上から外れないようにはしないとな、とはずっと思ってますね。
──それこそDJでもライヴでもやってて、エモーショナルになって冷静さが失われる、みたいな瞬間ってないですか?
Ali& めちゃめちゃありますよ、俺(笑)。
──そういう自分と、自分のポジションとかを冷静に見ている自分とっていうのはどういうバランスなんですか?
Ali& 結局、現場っていうのと音源って、ちょっとまた僕は違うと思ってるので。音源に関してはこれはやらなきゃいけない、現場としてはこういう動きをしていきたいなっていう部分ではやっぱりあるし。あと、やっぱり、トラックメイカーの若い子たちとか、先輩たちもいるし、僕らの世代もいますから。そういうところを見てて、どっちかに何かがかたよっていたらそれを戻したいなって思う気持ちもすごいある。そのために注目をどう浴びるか、注目を受けるにはどうするかっていう部分でもやっぱりちょっとは考えるし。たとえば、すべてを知った上で、今まであまりにもディープなものが多すぎたので、その反動でEDMに行ったっていうんであればなんとなくわかるんですけど、そうじゃなくて単純にEDMが流行ってるっていうか、楽しくなれるからっていうだけで行くのを──別にそれでもいいんですけど──ちょっとこっち側に引き寄せたいなって思う気持ちもすごいあるし。だから全然、EDMのイベントでも80KIDZで出る時もあるし。でもかけないですけど(笑)。僕らが持ってる最大限のそれで対抗しますけど。
──最大限アゲアゲのやつで(笑)。
Ali& そうですね。最大限のやつでなんとかわかってほしいな、みたいな感じでやりますけど。そういうところかなって思います。
提供:スペースシャワーネットワーク
企画・制作:RO69編集部