
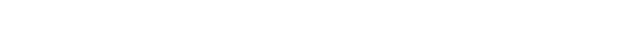
J、ソロアルバム10作目となった『eternal flames』のジャケットは、ベースが燃えた写真が使われている。まるでJのロックへの燃えない情熱を表しているかのような焔。実際、最新アルバムもメロディメイカーとしてのJの欲望が爆発しつつ、「歌う」ことへの表現が今まで以上に高まっている。「ロックへの情熱」がぎゅっと詰まっためちゃくちゃかっこいいアルバムだ。ロックの中心にいながら、常に新しいものを追い求め、エネルギーを発し続けてきたアーティストを衝き動かしているものは何なのか。今年頭にJバンドに復帰したmasasucks(the HIATUS、FULLSCRATCH)とともに、「バンドサウンド」に対する思いから「ロック」の精神論まで語ってくれた。
自分がロックミュージックに撃ち抜かれた時から好きなものって何も変わってなくて、今回やっと何か手にできたっていう思いはすごいあるんだよね(J)

──今年になってmasasucksさんがJバンドに復帰されたということで。ヌンチャクのごっちん(溝口和紀)さんとの強力タッグがライヴで観れるようになって非常にうれしかったんですが、今はどんな感じですか?
masasucks 和気あいあいとやらせてもらって、面白いですね。やっぱり一緒に音出してレコーディングしてても、Jさんのスケール感は会った時から変わらなくて、いつもいろんな垣根をぶっ壊そうとしていて。メンバーみんなでまっすぐ同じ方向に向かっていけるっていうのを、すごい体感してますね。
──masaさんとの最初の出会いを教えて頂けますか。
J 初代のフランツ(・ストール)の次にギタリストになる人間を探してた時に、いいギタリストがいるよ、っていう情報を得て、ビデオとか音源とかを聴いて。それで、彼だねっていうところで声をかけさせてもらったんだけど。当然フランツっていう、ScreamとかDYSとかやって、あの世代のいわゆるグランジの走りのムーブメントにいた人間の代わりなんていうのはたぶんいないし。だから、その代わりって意味ではないんだけど、でもエネルギーを持ってるギタリスト、そのヤンチャさみたいなものは絶対条件だったし。いろんな意味でギターが上手だったりする人たちはまわりにたくさんいたけれど、そういうものじゃなくて、必要なのは走り続けてるやつだよなっていうのは感じてましたね。
masasucks 感動ですね(笑)。
──バンドメンバーが一丸となって、非常にいいモードに入っているんだなと、この前の「Birthdayライヴ」を観てて感じたんですけど。
J そうですね。今回アルバムもすごくいいものができたし、自分たちが鳴らし続けてるのは、シンプルだけどタフじゃないとプレイできないような曲が多いから。そういう意味では、自分たちの挑戦をずっと続けてるバンドだったりもするんだよね。
masasucks 俺も、しばらくいなかった間でもライヴはしょっちゅう行ってたし、楽屋にもいたりして。ステージでプレイしなかったっていうだけで、空気感も変わんないし、違和感なくまた一緒にできるようになったなっていう感じはありましたね。
──そのライヴで、Jさんが「今作でまた新しい次元に行けた」って仰ってましたが、1曲目“Verity”の歌詞に《9番目の自由から 飛び出した原理》っていう歌詞があって。まさしく前作『FREEDOM No.9』で自由を求めてたところから、それを超えるものができたっていうのをすごく感じて。
J 実際ね、自由な生き方をずーっとしてきてる人間だから。前作で「FREEDOM」っていう言葉を使って自由を掲げたわけだけど、やっぱりいろんなリスクや責任みたいなものは当然あるわけで。実際自由になってみると、結構不安だったりする部分ってあると思うのね。縛られてるからこそ、自由を強く掲げる人たちも多いと思う。でもいざ自由になってみると、どうしていいかわかんない人たちも多いと思うんだよね。その中で自分としては掲げた以上は決着をつけなきゃいけない何かが当然あって、それを言わないと今作始まんないなと思いながら。
masasucks ははははは。
──あえて言い切ったところがあるんですね。
J そうなの(笑)。でも今回、気がつけば10作目っていう。いちベーシストがね、そんなにアルバムをリリースするなんてほんとにないことだよって言われたし。でもやってきたからこそ、立たなきゃいけない場所は当然あって。そこから逃げずに、力まずにその場所に立つために、その歌詞が必要だったのかな。
──確かに全体を通してメロディラインも歌詞も強いんですけど、すごく伸びやかなスケール感があって。すごくロックな作品ですよね。
J ありがとうございます。そういうスケール感とかサイズ感みたいなものは、自分自身がもともとロックミュージックに持ってるイメージだったりもするんだよね。広がっていったその中にどんな画が見えるんだろうな、リスナーのみんなはどうやって聴いてくれるのかな、っていうのは楽しみにしてるし。そういう意味では俺、LUNA SEAの時から見てる画っていうのはあんまり変わってなくて。自分がロックミュージックに撃ち抜かれた時から好きなものって何も変わってなくて、今回やっと手にできたっていう思いはすごくあるんだよね。
masasucks Jさんのその初期衝動っていうか、音楽に対する、ロックに対するパンチ感っていうのを、新たにこのアルバムで表現できたんじゃないかなっていう感覚はありますね。
J よりシンプルになってってる感じはすごいするんだよね(笑)。めんどくせえこと一切しない、みたいな。
masasucks はははは。
すごくシンプルな曲でも常に毒味があったり、ひねりが入ってたりとか、ひとつ面白いポイントが必ずどっかにあって、そこに挑んでるんだな、みたいなのを俺はデモの時に受け止めるんですよね(masasucks)
──そういうふうにシンプルに、ソリッドになっていくのはなぜなんでしょうね。
J 恥ずかしいんだよね。そういうの好きなのよ。好きだし、存在も否定しない。肯定のみなのよ。でも俺がやってきた道のりの中で、それだけになってしまうことの嘘くささっていうのもあって。だって俺、70年代に生まれて、80年代の音楽を聴いて、そして90年代も見てきて、今2015年でしょ。そのすべてをまとって今があるわけじゃない。そういう人間が発するべき音があると思うし、いつもそれを探してる感じはする。それが俺の中での今一番クールなことかなって。世代で区切られちゃう音楽もいっぱいあるじゃない。でも、その区切られちゃう音楽ではないほうを、自分の中から発していたいなって、ファーストアルバムの頃から思ってたし。いまだに自分がロックミュージックを聴き始めた時のアルバムは、今聴いてもものすごいかっこいいものとして存在してるから、そういうものを作りたいとも思うし。
masasucks レコーディングに入る時に、Jさんにデモをもらうじゃないですか。たとえばすごくシンプルな曲でも常に毒味があったり、ひねりが入ってたりとか、ひとつ面白いポイントが必ずどっかにあって、そこに挑んでるんだな、みたいなのを俺はデモの時に受け止めるんですよね。だからそれをいかに面白くアウトプットするかっていう感覚はずっとあって。だってね、10枚――あ、10枚おめでとうございます(笑)。
J ありがとう(笑)。気がつけば。
masasucks ものすごい曲数を作ってきたわけじゃないですか。もちろんボツ曲もあるだろうけど、そこに果敢に挑んでる先輩っていうイメージがすごいありますね。
──でもそういう挑戦をずっと続けていくのは難しいことなんじゃないかと思うんです。
J そうですね。やればやるほど刺激はなくなっていくし、やればやるほど満たされてはいくから。その中で俺を突き動かしてるのは何だろうっていつも思うんだけど、やっぱり渇いてんだよね。何かを作り上げると、またその次が見えてくるし。あんまりシリアスにならないようにわざとしてたり、どうやって自分をフレッシュな状態に置いとくか、みたいなのも自分のバランスの取り方で。不思議だよね、一番将来のことなんて考えてない人間だったから(笑)。















